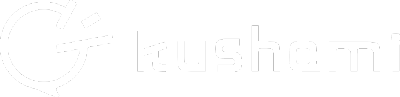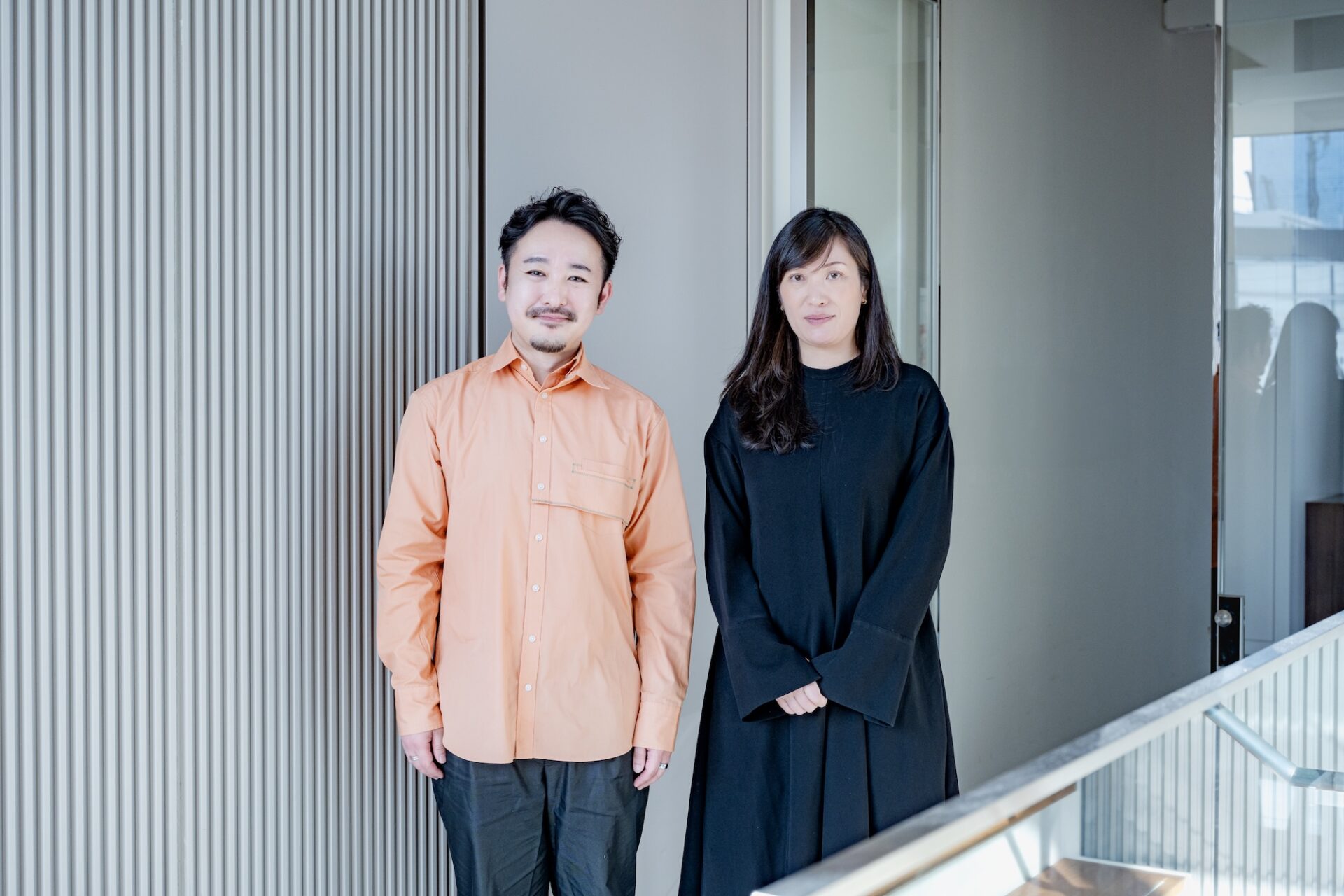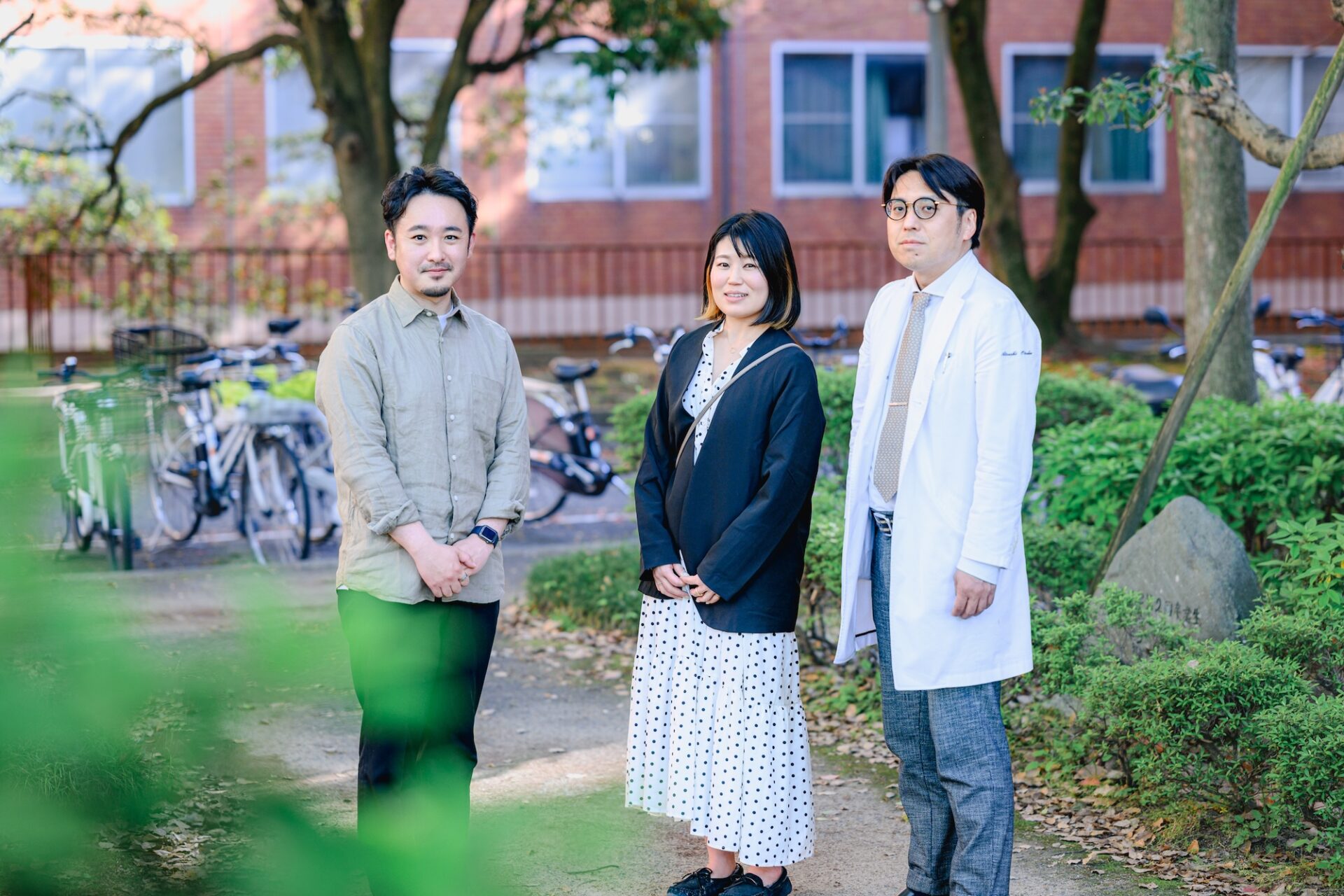ひとに、
企業に、
やさしい
PRを。
kushamiは、やさしさを強みに、
戦略設計から実行まで寄り添う
プロフェッショナルPRチームです。
kushamiの特徴
事業の
社会的価値を高める
PRパートナーとして
私たちが選ばれる
2つの理由
Our Key Features01
経済的価値だけではなく、
社会的価値を追求する
事業の支援に強み
Our Key Features02
企画立案にとどまらず、
施策を最後まで完遂する
責任を負う 「企画成立屋」
サービス
PRならではの視点を軸として、
様々な形で事業と社会のつながりを
設計しています
PR広報支援
「やさしいPR」で、はじめての広報活動にも寄り添います
PR起点のブランディング支援
社会との「つながり」から発想・設計するブランディング
PR起点のSNS支援
企業の価値を効果的に社会に届けるSNS運用
信頼の理由
医療・教育・まちづくり領域を
中心とした実績が豊富です
※過去にご一緒した企業・団体、これまでの支援したプロジェクトを一部含みます
メンバーコラム
kushamiメンバーが
PR視点で見つめたできごとを
綴っています
2026.02.02
LLMO時代、PRが主役じゃない?──検索からAIへ。「文脈設計」がいよいよ本気を出す説
この記事は、全てのPRパーソンが考えていることを代弁した記事です。 「やっと時代が追いついてきてくれました」 某PRパーソン談 デジマとPRと、わたし。 最近、こんな感覚ありませんか? 「Googleで検索するより、ChatGPTに聞いたほうが早いし寄り添ってくれてる気がしない?」 私自身、大学の卒業論文のテーマが「Google検索」でしたが(2009年)、いよいよコミュニケーションの主役が、検索からAIに移ってきたと感じます。 これまでデジタルマーケティングの王様だったSEO。キーワードを選んで、被リンクを集めて、上位表示を狙う。 もちろん、いまでも大事です。でも正直に言うと――それだけじゃ、足りなくなってきている。 ここで登場するのが、LLMO(Large Language Model Optimization)。 そして、この話を突き詰めていくと、ある結論にたどり着きます。 「いよいよPRの時代じゃね?」 LLMOって結局なに?めちゃくちゃ噛み砕くと LLMOの考え方は、意外とシンプルです。「AIに、どう理解されるかを設計しよう」これがLLMOです。 SEOは、人が手を動かす検索エンジン向けの最適化でした。一方、LLMOは“AIの頭の中”向けの最適化。 生成AIは、Google検索結果の順位表を見ていません。代わりに見ているのは、 こうした“世の中のテキストの集合体”です。 だからAIが答えを出すとき、こんなことを無意識に判断しています。 もはや私たち人間が色々検索したあとに、“解釈”というプロセスでやってることと同じですよね。 LLMO=PR発想のデジタル版 PRの仕事って、何だと思いますか? 「プレスリリースを書くこと?」「メディアに載せること?」 それも一部ではありますが、本質はもっとシンプルです。 PRとは、「世の中でどう語られる存在になるか」を設計する仕事。 これを考え続けるのがPRです。 ここまで読んでいただいてわかったと思いますが、PRってLLMOとやってることほぼ同じなんです。 AIもまた、「この会社、どういう文脈で語られてきたか」を見て判断します。 つまり、 LLMO=PR発想のデジタル版 と言っても、わりと過言じゃありません。 「SEOだけやってればOK」は、そろそろ限界 LLMOは、SEOの上位互換ではありません。むしろ、まったく別のレイ…
2025.12.30
AIは人を置き換えるものではなく、新たな「問い」を増やしたんだと思う
2025年のおわりに考える。AIと向き合い続けて分かったこと 2025年は、生成AIが「珍しい存在」ではなくなった年でした。生成AIは完全に「日常の道具」になりました。 kushamiの仕事の中でも、企画の壁打ち、構成の整理、リサーチなど、一日の時間の使い方として、AIと対話することが当たり前になっています。特に僕自身は、ChatGPTは月200$(3万円!)のProを利用していたり、Geminiで返信メールの下書きをつくってもらったり。すでに特別な存在ではなく当たり前の存在として、仕事とプライベート両面のバディとして常に自分の一番そばにいてくれました。 ただ、使えば使うほど、確信を持ったこと。 それは、AIは答えをくれる存在ではない、という事実。 「楽になる」はずだったのに、考えることが増えた 生成AIが普及すると聞いたとき、多くの人が思い描いていたのは「考える手間が減る」「仕事が楽になる」というものだったと思います。 実際、業務スピードは上がりました。情報収集も、プレスリリースの下書きも、打ち合わせの議事メモ作成も早い。 それでも、実際の現場で起きていたのは、考えることが減るどころか、むしろ増えていくという現象。 その答えは、「妥当」なのか。そして、「納得」(腹落ち)できるか。なぜ、今この切り口が必要なのか。自分は、どこに違和感を覚えているのか。 AIが出したアウトプットを前に、こちらが問い直される場面が、何度もありました。 AIの恩恵は「思考の速度」ではなく「問いの見える化」 2025年を通して感じたのは、AIがもたらした最大の変化は、効率化ではなく、問いの見える化。 AIは、こちらの曖昧な思考を、まずは言葉の形にして返してくれます。 すると、 「自分は、本当はこう考えていたのか」「この前提、どこから来ているんだろう」「この言い回し、誰の視点なんだろう」 といった問いが、やまほど出てくる。 AIは思考を代替するのではなく、思考を露出させる存在だったのです。 実際に使うときにはプロンプトを投げかけるときもなるべく背景情報や事実整理、自分なりの仮説生成をおこないます。そうすることで、より自分対自分、my思考 VS my思考'(ダッシュ)のやりとりに深まっていくのです。 2025年は、「AIがあるから考えなくていい」のではなく、「AIがあるから、より深く考えざるを得…
2025.11.06
PRはピントを合わせる仕事
PRは「発信」ではなく「ピント合わせ」 一般に「広報」や「PR」という言葉からは、大きなニュースリリースや華々しいイベントを通じて情報を拡散する姿が想起されます。しかし、kushamiは創業以来“やさしさ”と“実行力”を武器に、企業と社会の間に立って「世の中とのピントを合わせる」仕事に取り組んできました。 組織の内側と外側の間に立ち、社会の空気やトレンドを読み取りながらクライアントの思いや意図を社会の言葉に翻訳し、単に“伝える”のではなく“届く”形に整える。こうした境界線上の仕事こそが、PRの本質だと私たちは考えています。 kushamiの強み:境界線に立つやさしいプロフェッショナル kushamiの強みは、何よりも企業と社会の“境界線”に常に立ち続けられることです。 特に、経済的価値だけでなく社会的価値を追い求める企業を支援するのが得意です。創業以来掲げる「やさしいコミュニケーションで、やさしい世界をつくる」というビジョンのもと、ヘルスケアや教育、環境、地域創生・まちづくりなど社会的意義の大きな領域に挑戦する企業や団体を支援してきました。社会課題に取り組む組織ほどPRやブランディングの重要性は高いものの、リソースが限られている場合も多い。kushamiでは、そうしたお客様に対しても柔軟なサポートを提供し、長期的に伴走する体制を整えています。 また、kushamiの支援は広報活動にとどまらず、ブランディングやSNS運用、ウェブサイト制作といったコミュニケーション全体を設計・実行できることも強みです。以下に、主な強みを整理します。 これらの強みは、単に情報を拡散するのではなく、クライアントの価値や思いを社会的課題と結び付けて発信するためのものです。次に、具体的な事例を通じてkushamiのアプローチを紐解きます。 スピークバディ事例:個人の課題を社会課題へ引き上げる AI英会話サービスを提供するスピークバディ様では、CEOが兼任でPRを行っていた状況から、kushamiが初期PR立ち上げから内製化までを支援しました。kushamiは「英会話という個人の課題を社会課題へ引き上げる」方法論のもと、2020年から2024年までの4年間、PRの設計から実行フローまで地道に伴走しました。 当時、スピークバディでは社内リソースが足りず、発信内容や方法も手探り状態でしたが、kush…
おしらせ