プレスリリースの「型」を理解しよう
では、理想のリリースを描くには、何をどう書けばよいのでしょう?
まずは基本の構成をおさえましょう。以下の要素を順に整理していくと、メディアに届きやすい「ニュースのカタチ」になります。
①タイトル・サブタイトル
一番大切なのはタイトルです。
ここで、世の中に届けたいキーワードをしっかり盛り込みます。理想的には、「社会課題」×「あなたの取り組み」という構造になっていると、ぐっとニュース性が高まります。
例:
医師の働き方改革を実現する〇〇、「認知症エコシステム」構築を目指し、〇〇県と包括連携協定を締結
②概要説明
・誰が、何を、どのように実施するのか?
・その目的は何か?
読者が「つまり何をやるのか?」をパッと理解できるように、シンプルにまとめましょう。
③背景・社会課題提示
その取り組みが、どんな社会課題やニーズに応えるのか?を伝えます。
ここで「社会的な必然性」が感じられると、ニュースとしての説得力が増します。
④課題解決策説明(取り組み・商品・サービス)
その社会課題に対して、どのようなアプローチで取り組んでいるのか?
自社の技術や強みを説明するだけでなく、「誰と組んで」「どんな現象が起きて」「どんな人が救われるのか」まで具体的に描きましょう。
⑤ヒト(語り部)を登場させる
最後に、「人の顔が見えるストーリー」を入れると、ぐっと読まれやすくなります。
・当事者(患者、利用者、地元の人など)の声
・開発者や企業担当者のコメント
メディアが取材したくなる「語り部」を、あらかじめ用意しておくのもコツです。
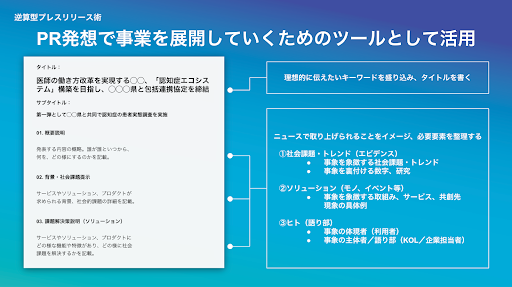
どこから手をつけていいかわからないときは
「そもそも、プレスリリースの書き方がわからない…」
そんな時は、無理にゼロから始める必要はありません。今は、ChatGPTなどの生成AIを活用するのも一つの方法です。キーワードや素材を入力すれば、それらしい“たたき台”が出てきます。
そこから自分たちの言葉で色を足していけばOK。まずは「それっぽい形」を作ることで、周囲と議論しやすくなります。
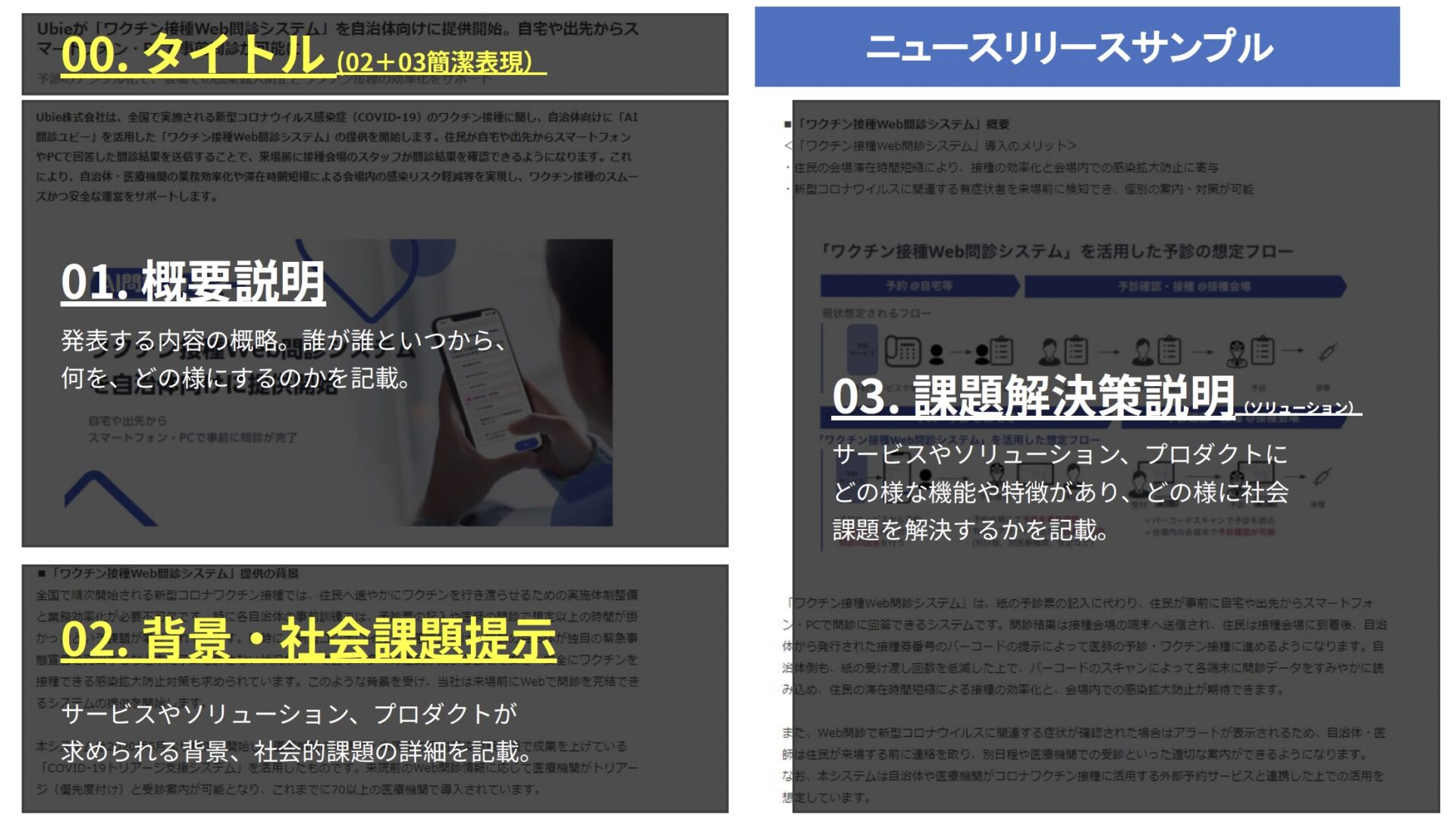
プレスリリースは“ニュースの部品”を届けるもの
勘違いされがちですが、プレスリリースは「完成したお知らせ文」ではなく、「ニュースになる材料(部品)」をメディアに渡すものです。
ポイントは、以下の3要素を盛り込むこと:
・社会課題・トレンド(現象の背景にある問題や数字)
・ソリューション(取り組み、商品、共創相手など)
・ヒト(語り部)(現象を体現する当事者の声)
この3つを組み合わせて伝えることで、メディアにとって取り上げやすいネタになります。
おわりに:小さく試して、大きく育てよう
最初から完璧なリリースを目指す必要はありません。まずは1本、理想のニュースを描いて書いてみる。そして、まわりの反応を見ながら、発信の精度を上げていけばいいのです。
あなたの事業や取り組みを「社会の話題」にしていくために。
プレスリリースという道具を、ぜひ育ててみてください。

