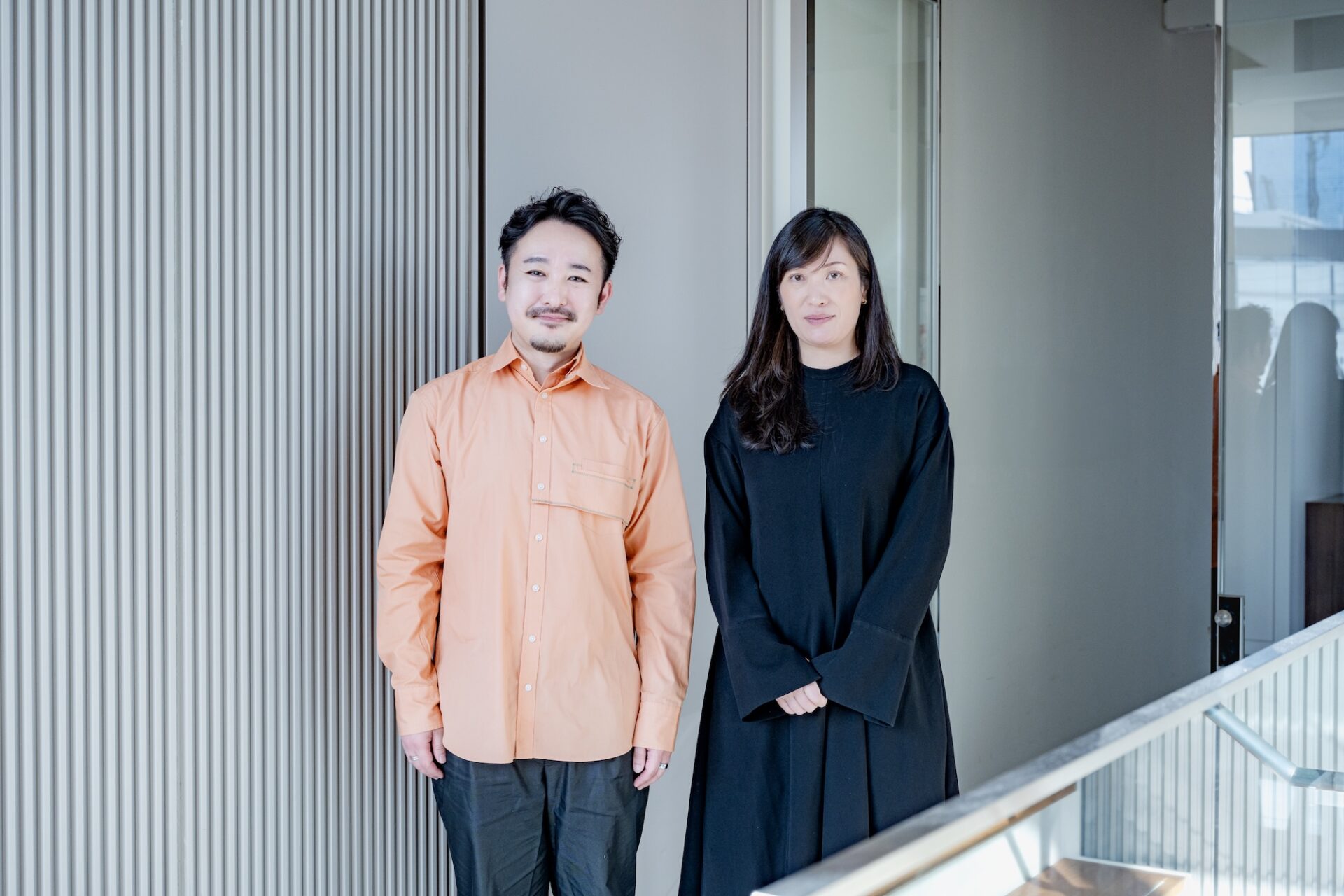学生と地域をつなげるきっかけになるミチシロカ
ミチシロカとはどういった事業ですか
地方自治体、学校と産官学連携をしたフィールドワークプログラムで、参加した学生の考える力や価値観を育成することを目指す教育・まちづくり事業です。2022年にはグッドデザイン賞も受賞しました。
私たちCCSは元々、文科省のGIGAスクール構想に呼応する形で、北海道内を中心とした地域の学校に対してコンピューター端末やWiFi環境を整え、教育現場でのIT導入を支援するといった事業を行ってきました。
小中学校や教育委員会との取り組みを続ける中で、未来の地域社会の礎を作るための教育ってどんなものだろうと考えるようになったのが、ミチシロカが始まったきっかけです。

地域の経済をよくするというと、外部から大きな企業や事業を誘致するという話になりがちですが、それだと本質的にはその地域のためにはなりません。実際、外部の資本が引き上げられてしまったら、その地域ごと大きく衰退してしまった例もあります。
外の力に頼らず、きちんと地域に足のついた事業を起こせる人を増やしていかなければいけないというのが私たちの考えです。
学生にとっても、ミチシロカを通じて「社会に対して価値を提供することが仕事なんだ」という感覚を持ってもらえればと考えています。現在の学校教育の流れからいきなり社会に出ると、働く意味がわからないまま就職することになってしまいかねません。そうすると、労働力としてしか自分を認識できない。私自身も、東京の大学を卒業して社会に出るときには、お金をもらうために自分の身を削ることが就職だと捉えていました。
でも、私は色々あって北海道にきたら、自分の力がちゃんと社会に還元されている実感を持てたんです。だから、「このまま就活することが自分にとってなんの意味があるのだろう」と悩んでいる学生さんには、地域でのフィールドワークを通じて、都市圏で当たり前とされている価値観や働き方とは違うロールモデルがあるということを知ってもらいたい。
受け入れ側である各地域にとっても、新たなまちづくりの視点を得て、地に足をつけた地方創生・地域創生につながる取り組みになることを目指しています。

プログラムの具体的な内容を教えてください
10名程度の学生が1週間自治体で共同生活を行い、その中でこちらのお題に沿った課題解決方法を考えてもらうPBL(Project Based Learning:課題解決型学習)式の教育プログラムです。例えば「真狩村の未来村長として、どのような地域づくりをしていくのか立案すること」といったテーマだけ与えて、最終日に成果発表をしてもらいます。
私は第一回のミチシロカに学生として参加しました。全体を通して「自分たちで考える」機会が本当に多かったです。フィールドワークを通して自分で考えたことをしっかり自分の言葉で表現できるようになったと思います。
今はネットで検索すればなんでもすぐ出てくるので、どこかで聞いた情報や誰かの考えを自分の言葉として話してしまいがちなんですが、そうではなく、ちゃんと自分の中から生まれた言葉が引き出された感覚がありました。

ミチシロカの特徴として、周りの大人たちは基本的に口出しはしませんし、テーマだけ与えてプログラムは白紙です。他の学生インターンプログラムを見ると、タイムテーブルがかっちり決まっていて、学生はその通りに動くだけということが多いのですが、ミチシロカはその真逆だと思います。
東京の「当たり前」からはみ出す生き方や、地域への眼差し
kushamiはどのような立場で支援したのでしょう
実は当初はPR担当者としてではなく、ミチシロカ開催中に学生たちを取りまとめてくれる役割を期待してお声がけをしました。イメージ的には「学生の一番近くにいる大人」のようなポジションで、相談があれば話を聞いてあげたり、スケジュールに関する約束事やアドバイスをしたりといった感じで、一見些細な役割のようですが欠かせない存在です。
また、私たちCCSがミチシロカの運営に関する相談をする壁打ち相手としてもご協力いただいています。
参加学生にとっては、kushamiの飯嶋さんは一番近くで見守ってくれる大人、という印象でした。今、私はミチシロカの第二回以降は運営側としてプロジェクトに携わっているのですが、運営サイドに入ってから、飯嶋さんが入交さんや川端さんの壁打ちパートナーとしての役割も担っていたことを知りました。
学生の目線だけでなく、企業やまちづくりの目線も携えて、今後のミチシロカに対してとても多角的な提案をしていて、勉強になります。
ミチシロカは、自分の頭で考えたものを自分の言葉で吐き出して自分でかたち作って、それがいかに世の中に貢献できるか、というチャレンジをする場所です。だから、繰り返しになりますが、でしゃばりすぎてはいけないし、先生的な立場も違う、かといって何も言わなすぎるのも意味がない。どのような距離感で関わり合うかは今でも難しさを感じています。

kushamiさんは最初に相談をした時から理解度が高くて、パートナーになってもらうならこの会社しかいないと今でも思っています。都内でインターンプログラムを運営されている方と何人もお話をしたんですが、ミチシロカが実現したいことをここまで深く理解してくれたのはkushamiの飯嶋さんだけでした。
僕自身、東京の大学を卒業して大企業に入った後、挫折や紆余曲折があって退職し、今kushamiという会社をやっています。いわゆる順風満帆なキャリアではなく、価値観が揺れ動いた経験をしています。だからこそ、ミチシロカが提唱する「自分にとっての価値を見つける」「学生時代に失敗できる経験を、地域の場で」という取り組みには強く共感しています。
また新卒の頃から日本各地の地域に根ざしたお仕事の機会に数多く恵まれるなかで、地域創生・地方創生への眼差しも培われていったように思います。僕は埼玉県鶴ヶ島市という東京のベッドタウンで生まれ育ったのですが、こういったお仕事の機会を通じて、「東京の“正解”が、必ずしも地域にとっての正解とは限らない」と強く実感するようになりました。
日々向き合っている「日本をより良くするために、誰もが暮らしやすい、やさしさにあふれたまちづくりとは何か」という問い。ミチシロカ立ち上げにあたる川端さん・入交さんの想いにも重なるものを感じています。
「1+1=2」ってみんな当たり前だと思っているけど、その当たり前が自分にとって意味がある人とない人がいるし、実際の世の中はそんなに単純に動いているわけじゃない。
単純な計算式の中で勝ち上がっていける人が組織で出世したり東京でうまくやっていける人なのかもしれないけれども、ミチシロカはそこからはみ出してしまうような人でも価値を発揮できる、その場所があることを伝えていきたいんです。
だから、それを肌感覚で理解してくれるという意味で、kushamiさんには安心して運営を任せられると感じています。

境界線上に立っているからこそ、適切な翻訳をしてくれる
kushamiはミチシロカにとってどんな存在ですか
最高のNo.2かな。しっかり寄り添ってくれるし、自分達では気づかないところに気づいてくれる。
内部の人間と同じレベルで想いを理解してくれながらも、良い意味で客観性を維持してくれています。

客観性があるから、外に対して伝わるような情報に翻訳してくれますよね。例えばラーメン屋さんって、ネットでの評価だと美味いか不味いかで片付けられちゃうじゃないですか。どんなに苦労して作ってもその一言で片付けられちゃうのは悲しいんですけど、苦労しないと実際に美味しいものができないのもまた事実なんです。そして、せっかく苦労して作ったものを美味しいと思ってくれた人がいるのに、その後関係が続かないのはもったいない。
好きと思ってくれた人に対して、もう少し深いところでつながっていてもらえるようなストーリーを発信するのは、kushamiさんが得意なところなんじゃないかと思います。自分たちのこだわりや苦労を、適切に世の中に向けて翻訳できる。
僕は自分自身が「すごい」と思ったものや人・取り組みを世の中に紹介したい、広めたいという欲が強いんです。ただ、例えばミチシロカを「1週間北海道に行けるプログラムだよ、面白くない?」って説明しても、本質的な価値が一ミリも伝わらないじゃないですか。いかに本質を突いた説明をして、それを理解した人が集まってくれるか、賛同してくれるかが大事だと思います。
自分たちの想いと社会の関心のバランス感を持つこと、常に内部と外部の境界線の上に立つということを意識しています。客観視しているけど、理解していないわけではない。同じチームだけどちょっと違う立場だからこそ発揮できる価値があるのかなと。

思いのある当事者が語りすぎると重くなりすぎることってあるじゃないですか。近くで見てくれるkushamiさんのような人が言葉にしてくれることで伝わりやすくなると思います。ずっと一緒に話をしているから本質的なことも理解してくれていて、安心できます。
もちろん専門である広報・PR面でもその特徴を活かしていただいており、kushamiさんにはミチシロカの運営サポートのみならず、ウェブサイトの構成やブランディング、コピーライティング、プレスリリース発信などもご支援いただいております。
実は当社はPRが大の苦手なんです。というのも、当社は総合行政システム開発会社なので、情報というのは守るもの。自ら情報を発信していく取り組みはこれまでほとんどしてきませんでした。そんな当社だからこそ、kushamiさんのように理解度が高く、適切に翻訳してくれる存在はありがたいなと思います。
ミチシロカの拡大に向けてよき壁打ち相手でいてほしい
今後kushamiに期待することは?
現在は北海道内で開催しているミチシロカですが、今後はエリアを広げていきたいのと、社会人向けにも展開したいというビジョンがあります。
個人的には、地域社会を活性化する話と、迷える若者たちが活躍する話が、ミチシロカを通して両輪で進んでいければ理想的だなと思っていますが、具体的な展開方法を模索中です。kushamiさんには今後もたくさん壁打ち相手になっていただいて、良い方法を見つけられたらなと思います。

あとは、今ウェブサイトに載っているコンセプト「“らしさ”をつくる、まちづくり。“らしさ”を見つける、ひとづくり」がもう3年経ったので、そろそろkushamiさんに手伝ってもらってアップデートしたいね。
確かに、そのコンセプトは立ち上げ当初のフィールドワークを中心に据えた中で出てきた言葉ですよね。数年経って、ミチシロカの価値やカバー範囲も広がってきているので、もう一度価値を見直して伝わる言葉に翻訳するお手伝いをしていきたいと思います。