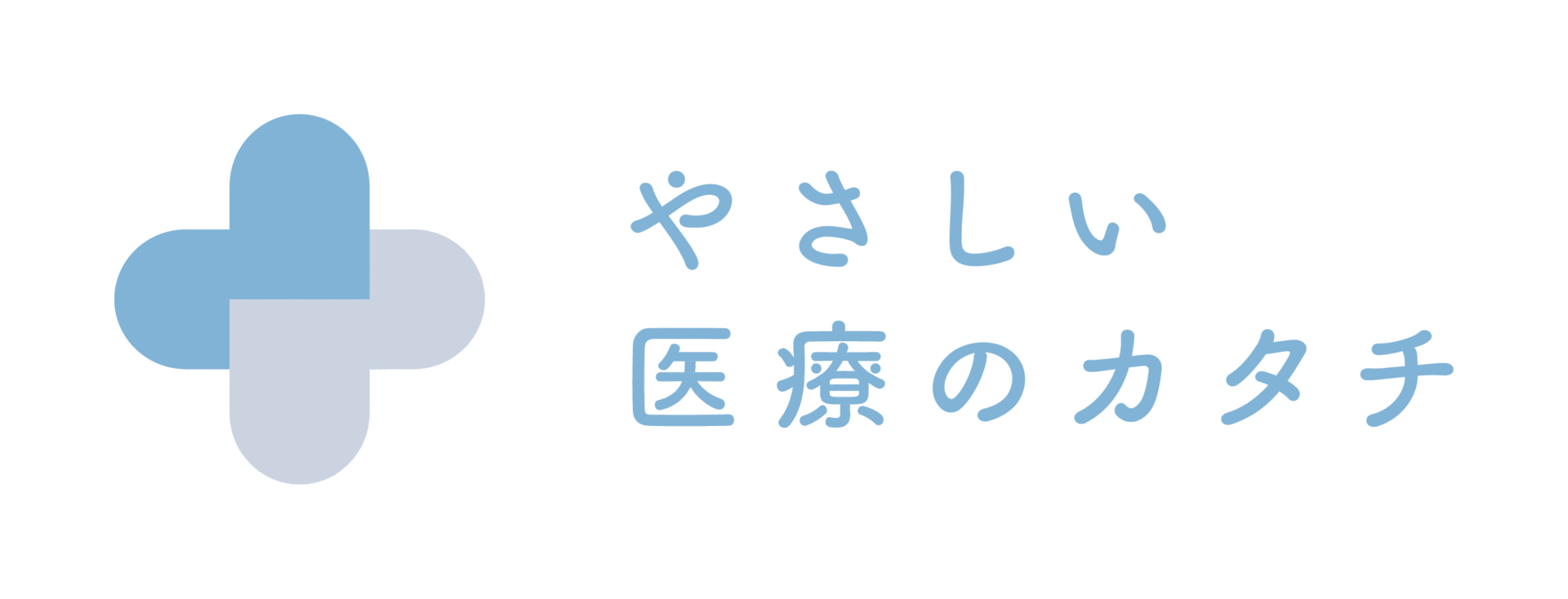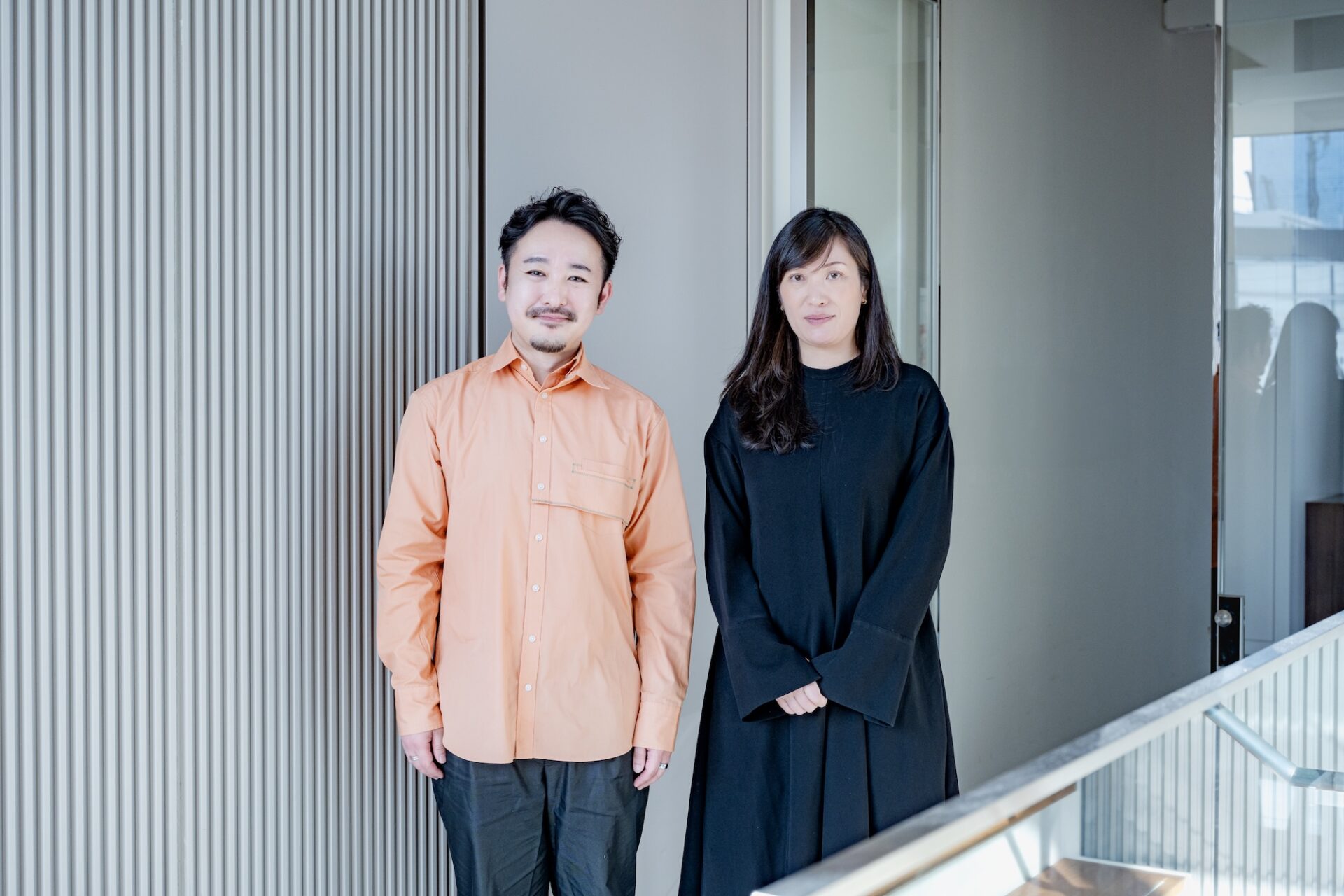医療従事者による医療情報発信アカウント
やさしい医療のカタチはどのような活動をしているのでしょうか
近年、医療技術の進歩には目を見張るものがある一方、医療を取り巻くコミュニケーションには課題が多く残っています。TVやネットでは「iPS細胞で難病が治る!」「がん免疫療法でがんが消える!」などのセンセーショナルな言葉が踊りますが、患者やその家族からするとどの医療情報を信じたら良いのかわからなくなっています。また、医者の一言に傷ついたり、家族が気持ちを理解してくれないなど、心のケアの遅れにも課題があります。
そこで、2018年、私たち有志の医療関係者で市民講座「やさしい医療のカタチ」を立ち上げ、医療とインターネットの普及に伴って生まれた知識や心のギャップを解消する活動を始めました。それ以来、YouTubeやX上での医療情報発信を行っています。一般の方に向けた医療情報に関する啓発イベントをリアルで開催したり、同人誌「医療のトリセツ」を出版したりと、現在は発信の場をSNSに限らず活動をしています。

活動体制としては、私大塚篤司(近畿大学医学部皮膚科学教室主任教授)、堀向健太(小児アレルギー科医ほむほむ・東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 小児科)、山本健人(外科医けいゆう・京都大学大学院医学研究科)の3名が中心となり、事務方を塩谷が担当しています。他にも、作家の浅生鴨さん、編集者のたらればさんといったの方々に関わっていただいております。
kushami飯嶋さんにはPRとしてイベントや広報活動全般の設計・監督を担当いただいております。kushamiさんが参画してから、広報に関して、とても楽になりました。
それまでもやさしい医療のカタチ以外の仕事でも他の広告代理店やPR会社とお仕事をすることもありましたが、一般企業のPR手法をそのまま流用されるケースが多くて、言葉選びや全体の設計に首を捻るケースが多かったんです。
医療のPRを専門的に手掛けている人に頼まないとイベントが成立しないんだなと思い、以前からお仕事でお付き合いがあり、医療系の実績があるkushami飯嶋さんにお願いをするようになりました。
医療PRとはどうあるべきか
医療におけるPRの難しさはどんなところですか
一般的な商材の広告やPRではビュー数やフォロワー数といった数字で見えるインパクトが話題になりがちですが、こと医療は、それらをKPIとして設定すると失敗する分野だと思います。あくまで患者さんやそのご家族向けのイベントや情報発信なので、あまりにも数字を意識してしまうと誰のための商品なのかわからなくなってしまうんです。
だから、バズらせようとか視聴者5万人を目指そうといった発言がメンバーから出たことは一回もないです。
やさしい医療のカタチのゴールは、一般の患者さんやご家族に興味・関心を持ってもらい、医療の誤解を解く、医師と患者さんの間にあるコミュニケーションエラーをなくすことです。だから、定量的な数値で表せるKPIを追いかけるのではなく、継続して発信し続けることが重要なのかなと捉えています。
一方、PR会社の立場として苦しいのは、スポンサーにお金を出していただくにあたって数字のアピールがしにくい点。製薬会社さんのようなスポンサーに広告料を出していただくにあたっては、やさしい医療のカタチはどれくらいユーザー獲得があるのか、メディアにどれだけ取り上げられているかという数値を求められます。だから、数値的な最短のゴールを達成するために、何か派手な仕掛けを打って注目を集めるという施策に寄りがちなんですが、それだけでは、本当に患者さんのためになっているのかというジレンマが生じます。
両者のバランスを取れるPR担当者が、医療の領域では重要です。
私は保育の事業にも関わっていますが、保育の業界でも、こういったPRやイベントをやろうとすると、結果としてユーザー不在になってしまっているケースをよく見かけます。ただ、やさしい医療のカタチの活動に関しては、活動に参加してくれている医師もメーカーも探り探りやっている感があって、さらにそこにkushamiさんが医療PRとはどうあるべきかをずっと考えながら組み立てているので、すごく丁寧なものが出来上がっているのが面白いなと感じています。
kushamiさんが一般的なPRのフレームを持ち込んでいないからこそ、理想の形になっているのではないでしょうか。
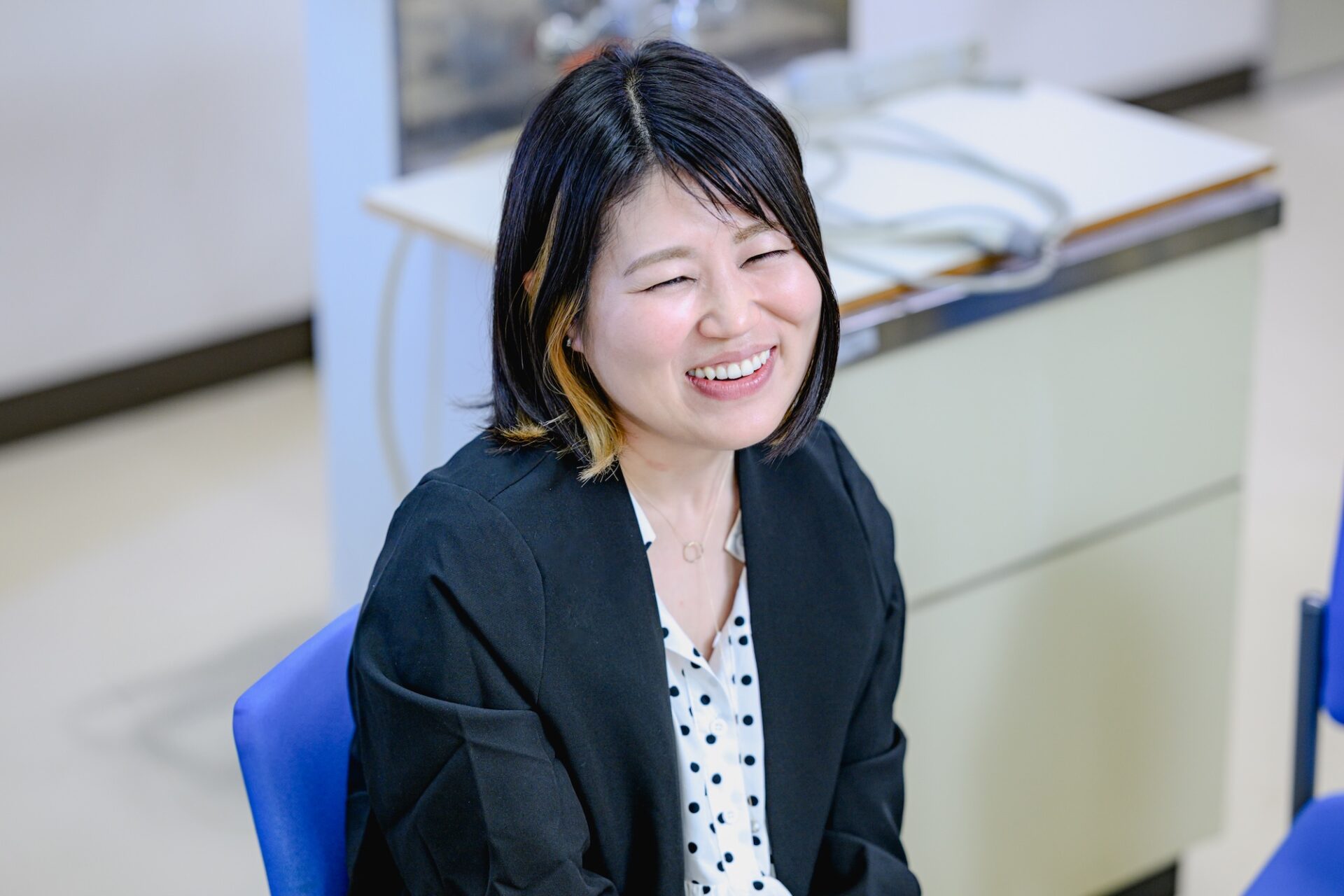
ありがとうございます。とはいえ、私も参画した最初の頃は医療のバックグラウンド知識が浅くてずれたPR内容を提案してしまい結構怒られていました。
他のPR会社さんと比べたら、そこまで大きくずれてないんですよ。ただ本当に細かい点で「ん?」と思うところが、当初はありましたね。
具体的には、ステレオタイプな医療者のイラストを用いたキャンペーン制作物を作ってしまったことが思い出されます。お医者さんが聴診器をかけていたり、看護師がナース帽をかぶっていたり、なんとなく赤十字マークをあしらってみたり(注:赤十字マークはジュネーブ条約により保護されており、医療機関・救護団体以外による使用は法律で禁止されている)。
今思えば、現場や実態を分かっていませんでしたね。
また、プロジェクト全体の設計として、当初は患者が置き去りになる危険性がある内容や、PRっぽいバズを狙った提案なんかもしてしまっていたので、そこは厳しくご指導いただきました。

それが今ではこんなに活躍されて、私たちにとって、いなければ回らない存在になりました。実に感慨深いですね。
PR会社としてはどうしても数字も追いたくなるんですが、数字を追うことによって患者不在になってしまうことは避けなければなりません。その象徴的な出来事がクラファンキャンセル事件でしたね。
クラファンキャンセル事件を経て、医療情報発信の最後の砦へ
どのような経緯でクラウドファンディングを企画しキャンセルしたのでしょうか
2022年にイベントをやるための費用が捻出できないという話になり、じゃあクラファンをやろうと決めました。かなり話を詰めたんですが、クラファン開始日の前日に「やっぱり患者さんのためにならないのでキャンセルしたい」と話をひっくり返しまして。クラファン会社の人をはじめ、協力してくれた人全員に平謝りするということがありました。
話を詰めれば詰めるほど、クラファンにお金を出すのは患者さんで、そのお金で患者さんのためのイベントをする、という構図に一同が違和感を覚えてしまったんです。
当事者から巻き上げるようなことはせず、自分達の手弁当でできる範囲にとどめておくべきじゃないか、でもこのタイミングでは非常に多くの方々にご迷惑がかかる…と、議論が紛糾しましたよね。キャンセルの件をはじめて聞いた時は、事務局として「ええっ」と驚きましたけど、英断だったと思います。
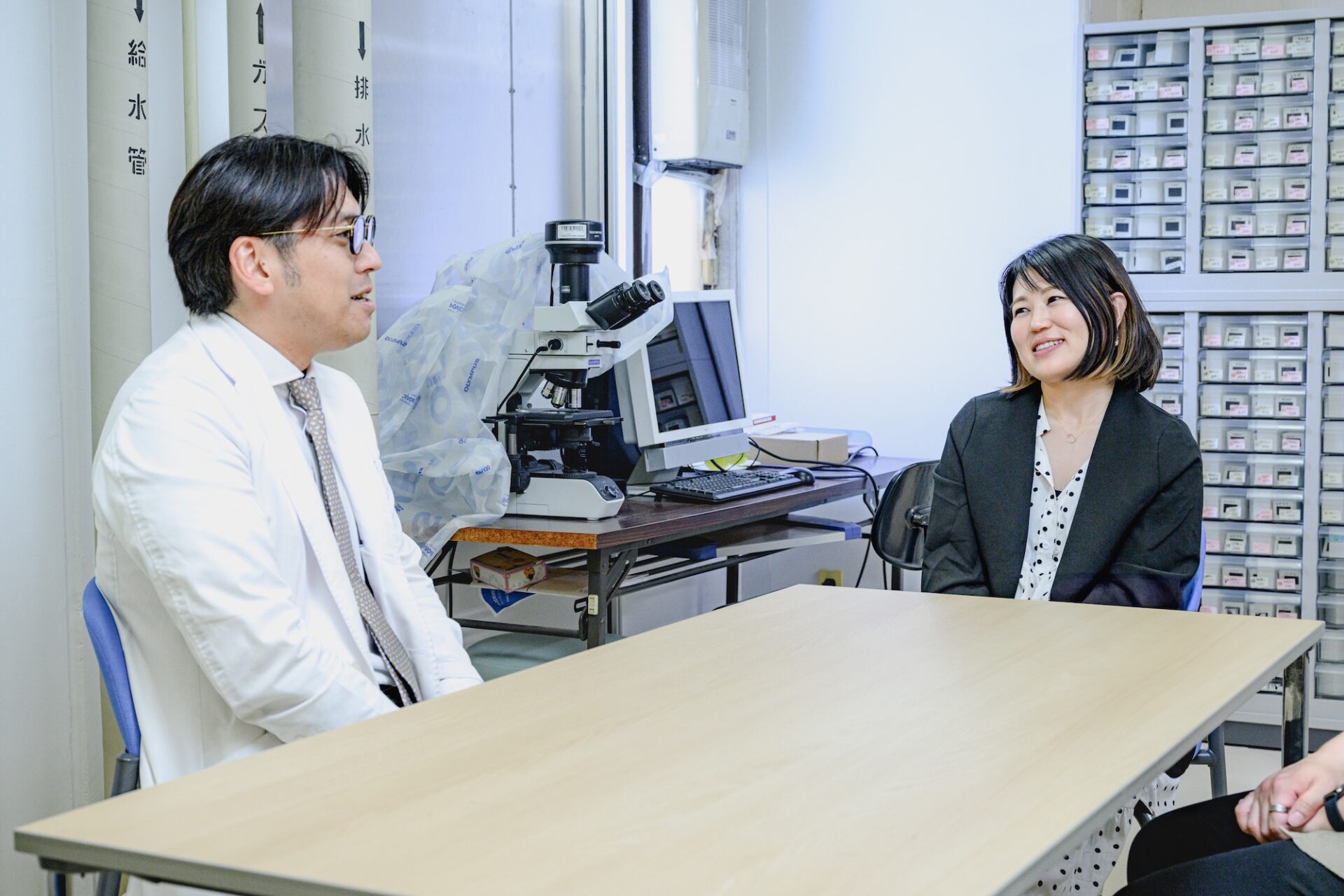
今振り返ると、クラファンをあの時やらなかったからこそ、やさしい医療のカタチがいまだに信用されているのだと思っています。当時はコロナ禍だったということもあり、医療不審がかなり可視化されていた時代でした。2025年現在では医療に関して発信するSNSアカウントも増えていますが、私たちやさしい医療のカタチは老舗として、変わらないスタイルでやっていけています。
SNSでの発信が当たり前になった一方、目立つハードルは上がった
専門家・医療者の発信についてはどうお考えですか
7年前にこの活動を始めた際はすごく珍しい目で見られました。医療従事者としては異端の存在だったんです。当時はSNSで発信している医療従事者はほとんどいなかったので、やる側としてはかなり覚悟を持って取り組んでいました。もしかしたら上から目をつけられるかもしれない、学会から何か言われるかもしれない、医療業界から弾き出されるかもしれないみたいな不安をみんな持ちつつ頑張っていました。
今では学会も公式SNSを持っているところが多いですし、医師が実名で情報発信することも普通になっているので、当時と比べてやりやすくなりました。

ただ、一方で今からSNSで目立った存在になるのは非常に難しい。もし、私が今から初めて情報発信を行うのであればSNSはやらないでしょうね。それくらいSNSは高い山になってしまいました。昔はSNS自体が小さい山だったので、自分がそんなに高く登らなくても山が成長するに比例して高い位置に行けましたが、今ではふもとから登ろうとすると相当な覚悟や努力、才能が必要です。
奇抜なことをやろうとする医療従事者も増えましたし、目立つためにはフォロワーを1万人まで増やそうという発想になります。
そうなると、目的が情報発信ではなく数字を追いかけることになってしまい、医療の情報発信としては望ましくない結果になってしまいますよね。
利害関係者が多岐にわたり、公益性の高い情報を扱う医療広報においては、そのようなテクニカルな面だけではなく、中長期的な視野に基づいた丁寧な設計が必要だと考えています。
「やさしさ」に込めた意味
kushamiもやさしい医療のカタチも「やさしい」がキーワードになっています
私たち株式会社kushamiは「やさしいPR」というコピーを掲げているんですが、インスピレーションをもらったのは、やさしい医療のカタチのコピー「やさしい医療」なんです。
やさしいにも色々あると思うんですが、やさしい医療のカタチにおける「やさしい医療」とは、カインド(=親切)、イージー(=容易)の両方の意味を内包しています。医療情報を発信する上で大切だと、私たちが共通認識しているアイデアです。
でも、実は運営している私たちが元々そういうやさしさを持っている人間かというと、実はそうではないです。やさしくない自分を知っているから、やさしくしようという自己暗示みたいなコピーなんです(笑)。
先生方の活動を見ていく中で「やさしいってなんだろう」と今でもずっと考えています。厳しいことを言うのもやさしさですし、現実を踏まえて話をするのもやさしさですよね。
社会とのより良い関係を作るために、様々な立場の生活者の方と双方向のコミュニケーションが求められているPRの文脈でも、「やさしさ」が重要なテーマだと思っています。
活動にご一緒させていただいてから何年も経ちますが、お仕事でもプライベートでも、ずっと大切にしている言葉です。

医療キャラバンで市町村を巡りたい
やさしい医療のカタチの今後の展望を教えてください
毎年夏にトークイベントを開催しており、今年(2025年)も新たなカタチのものを実施予定で、少しずつ企画についてメンバー間で話し合っています。
医療エキスポのような大掛かりなイベントもやってみたいけれど、人もお金も集めなければならず、ハードルが高い。各地の市町村で市民公開講座をやるのはどうでしょう?キャンピングカーやワゴン一つで行って「医療キャラバンがあなたの町で公開講座やります」なんて。
自治体と連携して、市役所の前の広場や公民館を貸してもらえるのでは?面白そう!
…いつもこんな調子で、企画会議が盛り上がりすぎて脱線してしまうんですよね。
やさしい医療のカタチの面白いところって、先生たち自身が楽しんで企画しているところだと思うんですよね。楽しんでやっているからこそ、アカデミックな堅苦しい感じではなく、医療情報として一般に伝わりやすいものになっているのではないでしょうか。