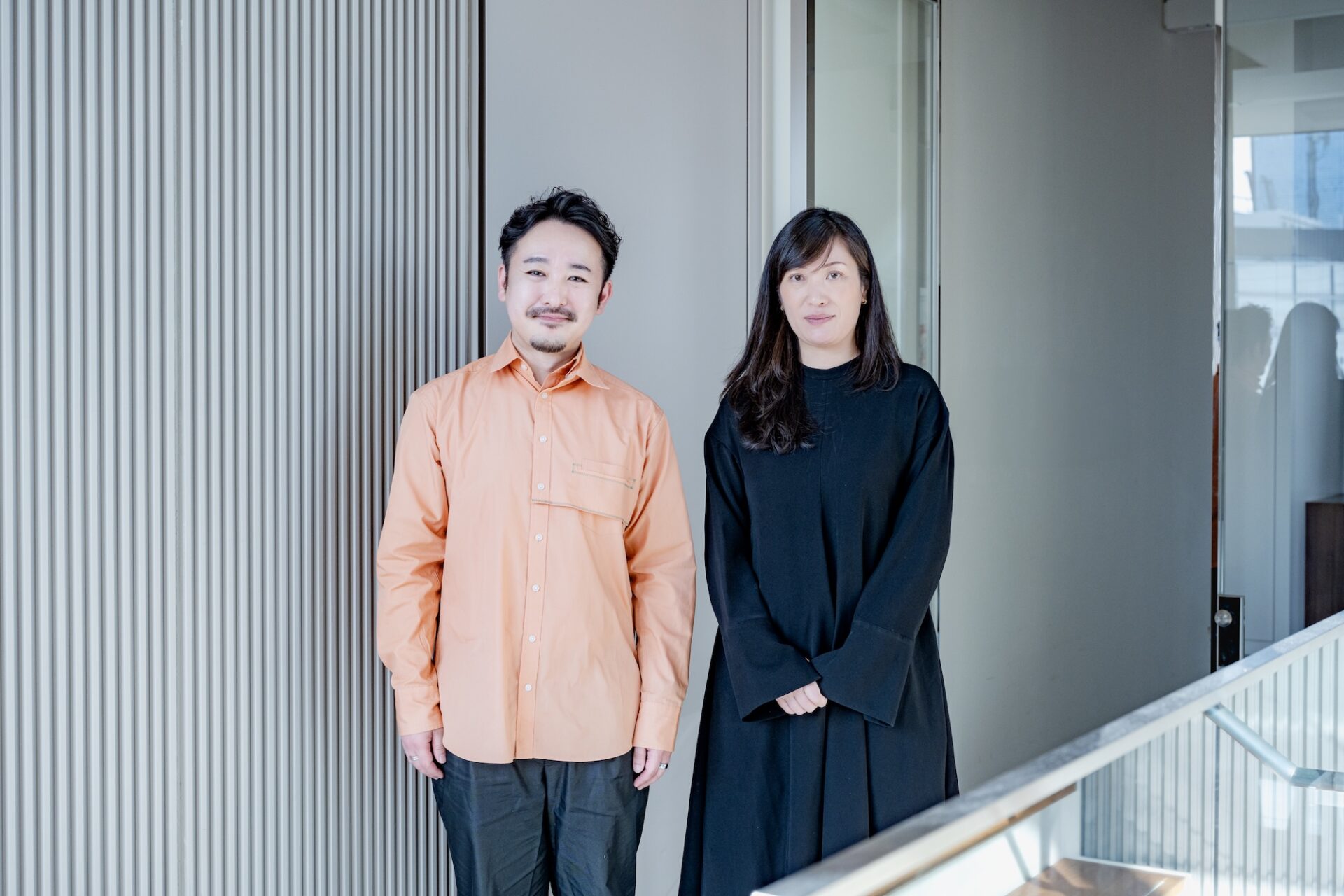暗中模索だったPRに道筋ができた
そもそもスピークバディはPRにどのような課題を抱えていたのでしょう
創業からしばらくは、社長である私がPR業務を行っていたんです。ただ、社員数が20名を超えるくらいで、私の方で手が回らなくなりました。そこで、既存のメンバーに兼務で担当してもらったこともあったんですが、やはり他業務のリソースを圧迫してしまったりということが起こりました。
発信する内容もやり方も「これで良いものか不安」と暗中模索の状態だった際に、PRのプロに伴走してもらいながらPRの戦略立案からアクションまで一気通貫で対応してもらうことが最適と考え、kushamiさんに入っていただいたという流れです。

立石さんは社会課題だったり、世の中が何を求めているのかをしっかりわかって話をされたり文章を書かれていたので、当初顕著な問題があるとは感じませんでした。
ただ、PRには対メディアのお作法的なものがあったり、どうやって取り上げてもらうかという戦略的なところが必要になるので、私の方でそれらの交通整理を行ったというイメージが近いかなと。
メディアの方ってある意味特殊で、何かご連絡しても返信がないことも多いし、ものの見方や時間の流れ方が見えづらいと考えていました。だから素人がコミュニケーションを取るのはハードルが高いんですが、そのあたりもkushamiさんが入ってくれてスムーズになりましたし、企画を持ち込んで取り上げられる頻度も上がったように感じます。

PRとマーケティングは役割が違う
スピークバディ様では、そもそもPRの重要性をどのように考えていましたか?
自社のサービスや価値観を広く世の中に知ってもらう手段として当社にとっては欠かせないものでした。
発信活動という括りでいうと、SNSやWebを活用したマーケティングも近しく語られがちなんですが、実際には施策を行なった後に成果をどう評価するかの指針が全く異なります。
マーケティングの領域だと獲得効率などの数字を基準に成果を判断すると思いますが、PRはそもそもフィールドがメディアということもあり、直接的かつ直近の数字に表れづらいことも多いと思います。
当社でも元々マーケティングの一部門としてPRがあったんですが、現在は一部門として独立しました。やはり評価の基準や目指すものが違うので、今の方がよりPRらしい活動になっていると思います。

評価するスパンの長さも、PRはマーケティングより長期的なスパンで見ないといけないですよね。何か一つの施策で成果を出すと言うよりは、長期的な流れの中で醸成されていくのがPRであるというのが正しいと思います。
私たちPRパーソンの存在意義は、企業と社会の間(境界)のポジションにいるからこそ、世の中の課題を可視化し、解決するきっかけを提示することだと考えています。
例えばスピークバディ様のPRでは、日本の今の円安傾向、日本企業の成長の鈍化といった社会課題を、英会話という観点から変えられるといった道筋を描くといった思考が求められるんです。

生成AIの隆盛、インバウンド需要がPRの追い風に
kushamiがスピークバディのPRに参画した当初から今までの社会状況と、どのようなPR活動を実施したのか教えてください
まず、当社が参画した2020年当時はコロナ真っ只中で、リモート、オンライン学習の需要が大きくなっており、スピークバディにとっては追い風となっていました。一方生成AIも盛り上がりを見せ始めてはいたものの「AI」というと新しさは感じられるもののまだまだ信頼度が低く、AIによる英会話学習はまだ本流とはなりきれていない状況でした。
それが2022年から2023年にかけて、ChatGPTの普及を機にAIについて「役にたつ」「信頼できる」という印象が強まり、さらにコロナが落ち着いてインバウンドが回復したタイミングで、スピークバディにとって再びビッグウェーブが来た。しっかりPRをして高い認知を得ることが求められるタイミングで、石原さんが広報・PR責任者としてご入社されました。
入社後、メディアの方々と会話していると「AI相手に英会話って気軽だし便利ですね」「日本人って英語苦手だし、関心持たれると思う」という話にはなるんです。でも「今取り上げる必要性がある話」にはなりづらいんだなと感じていました。
ただ、英会話学習はどうしても個人の課題になりやすくて、社会課題になりにくい面があります。これをどうやって社会課題にしてメディアに取り上げてもらうかがポイントでした。
例えば、英語力がないと国内企業の海外事業が伸びづらいとか、インバウンド訪日客が増えているのにおもてなしがうまくできないというのは社会課題じゃないですか。こんなふうに、どういう切り口からみんなの課題に昇華するかについて、kushami飯嶋さんと壁打ちを繰り返していきました。
壁打ちをした内容をもとに、プロモートシート(メディア向けに取り上げてほしい内容を記したシート)を作成してくださり、それを持って私やkushamiさんがテレビ局や新聞社などのメディアさんにアプローチするといった感じで日々開拓を進めました。

今は主に私がメディアの方々との関係構築を担当しているのですが、プロモートシートをはじめkushamiさんが作ってくれた武器がたくさんあるので、それを活用してとてもスムーズに提案できていると思います。
やはり自社の持っているサービスを社会課題とどう結びつけるかというのはどの会社も苦労しているので、そこに関してプロの視点で道筋を作るサポートをしていただけるのは助かりますよね。

社会課題型のPRとはなにか
kushamiと他のPR会社の違う点はありますか
他のPR会社さんとも話をしましたが、イベント実施などインパクト重視の施策の話になることも多いので、そこは大きな違いですね。今取り組んでいる社会課題発信型のPRはkushamiさんならではだと思います。
飯嶋さんからご説明を受けて印象に残っているのが、世の中に新しい価値観を持ち込もうとする(=シェアオブマインドを獲得する)ときに、「提言型」と「PRイベント型」と「社会課題発信型」のPRスタイルがあるということ。「提言型」は例えば女性の働き方とか母親業に対する印象を変えることによって何かを行おうというものですが、これはもともとネームバリュー・発信力がある大手企業だからこそできるもの。「PRイベント型」も大規模なイベントを打つのが前提なのでやはりお金がかかる。一方、「社会課題発信型」であれば、今の自分達の体力でできることを一緒に考えながら進められるということを丁寧にご説明いただきました。
社会課題発信型のPRは、社会との対話を通じて「世の中ゴト」となるような“社会記号”を見出して種を撒いていくという工程で行います。小さな取り組みが多いので、すぐに効果が出るものばかりではないですが、それが広がっていつしか世の中ゴトになり、それに自社サービスが貢献するという流れを作るのが大切です。
スピークバディの皆さんがそもそも高いPRリテラシーをお持ちで、短期的な評価軸だけでなく長期的な視点で広報活動を捉えていただいたことで、社会課題発信型のPRがうまく機能したのだと思います。
あと、kushami飯嶋さんは半分社内の人みたいな感じで加わってくれて、メンバーとすごく仲良くされていましたよね。PRという仕事は、社内からのマメな情報収集や社内の方に動いていただきながら成立することも多いので、そんなふうにコミュニケーションを取る姿勢が素晴らしかったと思います。よく社内を知る分だけ、報告や提案も深かった。
他社だとやはりそこまでは深く関わってくれないので、お願いしたけど思ったより機能しなかったということも実際ありました。キャッチーな施策は企画提案してくれるんだけど、実際に運用やその準備までは関わってくれないので、実行しきれないとか思った結果と違ったとか。kushamiさんの場合はちゃんと風呂敷を畳んでくれる安心感がありました。

4年間蓄積した知見でPRの内製化を実現
現在、スピークバディのPRはどのような体制で行なっていますか
当社は2024年に伴走支援から外れ、現在は石原さん・伊藤さんの2名体制となっています。スタートアップのPR支援に入らせていただく場合も、最終的には蓄積した知見をもとにPRを内製化すべきだというのが我々の考えです。伊藤さんが加わったタイミングで、スピークバディ様での初期PR立ち上げにおける当社の役割は一旦終わったと捉えています。
私は2024年に入社したのですが、その時点でkushamiさんが整備してくださっていたPR業務関連のドキュメントがしっかり残っており、それをみればこれまで何をしてきたのか、これから何をやるべきかが大体理解できる状態でした。
私の入社前に蓄積した社外関係者との資料や議事録などをそのまま残してくれていたので、ほとんど困ることなく業務に入れました。
PRを内製化して、PRの専門人材を配置できたことは本当に良かったと思っています。スピークバディの初期の頃に、広報・PR業務を誰が担当するかについて周囲の経営者に相談すると、「採用部門や総務系の文章書くのが上手い人に任せてみては?」という答えが返ってくることがすごく多かったんです。でも、私が一人で担当していた時も相当苦労しましたし、PRは片手間でやって成功するものではないと思っています。
やはり戦略的、長期的にやって、3年後くらいに初めて結果が出てくるというものなのではないでしょうか。その頃には社内の人材も育ち、専門人材の採用もしやすいフェーズに入っているはずです。

初期スタートアップのPRも、kushamiとなら実行に移せる
kushamiをどんな会社におすすめできますか
これから初めてPRをやるにあたって暗中模索な状態の会社におすすめします。スタートアップでまだ人も少なくて、社内にPR経験のある人もおらず、かといってPR人材の採用はハードルが高いという状況で、kushamiさんのようなプロが伴走してくれると助かりますよね。
スタートアップの最初の頃は、戦略ももちろんですが、実行してみて、それを戦略など道筋に反映させて、という両方のプロセスが大切だと思います。kushamiさんは戦略だけでなく組織の特性に合わせて実行まで導いてくれるので、PRの初期段階から参画されることで迷走することを防ぐことができるのではないかと思います。